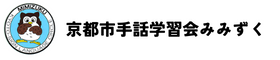はじめに
日本で初めて設立されたという手話サークル「みみずく」。正式名称は、「京都市手話学習会『みみずく』」と言います。
以前会長をされていた 八木勝光氏(現 特別養護老人ホーム淡路ふくろうの郷事務長)の書かれた「みみずく」会の記事や「京都市手話学習会 みみずく~25年のあゆみ」などを参考に、「みみずく」会の紹介をいたしましょう。
みみずく設立の経過
京都市手話学習会「みみずく」は、1963年(昭和38年)9月発足となっています。その設立のきっかけは、当時 勤労学生であった京都第二日赤病院のN看護士さんが、自分の受け持ちの聴覚障害をもつ入院患者n先生(当時、京都府立ろう学校教諭)により良い看護を…という立場から、まず、n先生とのコミュニケーションを成立させねばならないと考えたことに始まります。Nさんは、これを単なる個人的な職業意識としてとどめず、その当時彼女が通っていた同志社高校(定時制)の仲間を集めて、集団的に手話を学習する活動を始められたのです。
その当時は、まだ手話を否定こそすれ、自分から進んで手話を学ぼうなどという人は、ごく一部のろう学校教師や、ろうあ者の家族を除いては稀だったようです。今、(社会福祉法人)京都聴覚言語障害者福祉協会の理事長をされている高田英一氏は当時を述懐して、次のようにいっています。「みみずく会が出来た頃、これで耳の聞こえる仲間ができた。うれしいと思いながらも、なぜ、このように自分たちに直接関係のないことをやってっくれるのだろうと、半ばけげんな気持ちで、いつまで続くのやろうと、半ば不安な気持ちで、毎日曜日に、手話の授業のため、福祉センターに通ったものです。」
当時、全国的にみて、個人的に手話通訳活動に励んでいる人はあったものの、若い人達を中心に集団的に手話を学び、ろうあ者と交流する活動形態をとったのは、みみずくが最初であったのでは…と思います。
そして、従来、この種の活動にみられた奉仕活動から脱却し、ろうあ者と手をつないで、差別や偏見をなくし、解決していこうとする社会活動として展開したところに当時としてはユニークなサークルであったと考えられます。
「みみずく」その名称の由来
「みみずく」という一風かわった名称が付けられた由来について触れてみたいと思います。古い会員などから聞きますと、このサークルの名称にはおおむね三つの理由があるのだそうです。
まず、「みみずく」という鳥は夜行性であり、定時制高校へ通いつつ、手話サークルという、これまた夜行性の活動をやっていく、これはまるで鳥の「みみずく」と同じではないかというのが、その1つです。
次に「みみずく」とよく似た夜行性の鳥に「ふくろう」というのがおります。この両者をよく観察してみると、「ふくろう」は頭部が坊主のようなツルンとしていますが、「みみずく」には何やら耳のようなものが、頭部にのっかています。しかし、実際は毛が逆立っているだけであり、耳の役割はまったくはたしていません。人間様と鳥を一緒にするのは失礼だけれども、ろうあ者の耳もこれと似ているのはないかという発想が第二の理由です。
そして最後に、耳の不自由なろうあ者と常に歩みを共にし、ろうあ者の耳がわりとなれたらならば、ろうあ者に「耳がつく」ことになる、「みみつく」→「みみずく」というのが第三番目の理由です。多分、結成当時の仲間が頭を寄せ合って絞りだしたものでしょうが、うまく考えたものです。
現在の「みみずく」会
現在の「みみずく」会の会員数は、約300名。11支部14会場での例会を中心に活動しています。全体としては「京都聴覚言語障害者の豊かなくらしを築くネットワーク」の組織団体として加わり、聴覚言語障害者との共同の運動に参加しています。
"緑綬褒章"
京都市手話学習会「みみずく」は平成十八年(2006年)四月二十九日、
その長年に渡る活動の功績を認められ国より労いの賞状をいただきました。
私たちはこの賞を日々眺めながら改めて気持ちを初心に戻し、これからも活動に励みたいと思います。
京都市手話学習会「みみずく」記念誌
「みみずく」会は、その歴史の中で節目節目に それまでの活動をまとめる取り組みをしてきました。これまでに「15周年」「20周年」「25周年」「30周年」、「40周年」それぞれの年に記念誌を作っています。これらは 現存する部数がわずかであるということ、内容的に貴重な資料も多々あることなどから、このWEB上に上辞し、保存しながら多くの人々の前に公開をしてゆきたいと思います。