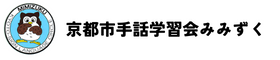みみずく学校 2008年11月16日(日) 持田隆彦
はじめに
昭和38年、当時府立ろう学校で教鞭を取る傍ら、京都市ろうあ協会の会長をやっておられた西田一先生が、京都第二日赤病院に入院されたことがきっかけで誕生した“みみずく会”です。
“みみずく会”創立40周年を記念して、“みみずく会の縁(ゆかり)の地を探訪して40年前を振り返り当時を偲ぽうと企画し、歩いたのが2002年10月6日(日)もう6年が過ぎた。そうして、これまで3回企画したが、暑かつたり、雨が降ったり、寒くて小雪が舞ったりと大変な日々でした。今回は、果たして大丈夫かな?
府立勤労会館

京都テルサの軽野政巳氏より写真提供
烏丸丸太町を南に下がった東側。現在は『ハートピア京都』になっています。
昭和41年3月にオープンした、この勤労会館を“みみずく会”の定例会場にしたのは、はっきりしないが、 41年の5月か6月ごろからと思う。
私、持田が入会した昭和42年6月22日(木)から、そう遠くない日だろうと思う。
七階の―番小さな和室7号、8号室が、夜間2時間700円だったと思う。年会費600円の時代、毎週木曜日とはいかず、時々お寺や、島原口の社会教育会館を利用していました。
昭和42年(1967)京都市からの助成金10万円を得る前後から会員も急速に増え、北区のろうあセンターが開設するまでは、この勤労会館が“みみずく会”の例会々場であり、ろうあ者のたまり場でした。
みみずくの15周年記念集会など、平成3年の廃館まで事あるごとに利用していました。
京都府立身体障害者福祉センター

昭和30年(1955)12月1日午前10時から、下鴨神社境内で開所式が開かれました。
全国に先駆けて身体障害者更生相談をはじめ盲、ろう、肢体障害者などの生活訓練、職業訓練を行う更生授産施設並びに、更生医療整形外科病院及び義肢補装具の製作修理施設などを、一か所に配置して身体障害者の総合的福祉施設が誕生しました。
ろうあ者更生施設も翌31年増築され、活版印刷機、名刺印刷機などを備え、活字ケースの配列順序植字、文選校正刷、解版などの指導をするもので、第一回入所生は5人。また、ろうあ課を設け、ろうあの母をもつ向野嘉一氏が手話のできる指導員として採用されました。後にろうあ課々長に就任。
この向野さんを、後に第二日赤の看護学生中島千代美さんが訪れて、みみずく会が誕生したことが、今日のみみずく会、いや、ちょっと言い過ぎかも知れませんが、ろうあ者福祉の充実の元になったことは間違いありません。
この府立身体障害者福祉センターは、発展的解消して城陽市に移転してしまった。したがってこのセンターで生活訓練を受けているろうあ者の受け入れ先が急がれ、いこいの村建設運動が始まりました。
みみずく会をはじめ、ろうあ協会の事務所や連絡先がこの福祉センターに置かれて居ました。
現在は昭和59年(1984)3月から京都府立視力障害者福祉センターとしてはり、きゅう、あんまなど、視力障害者の更生訓練施設に様変わりしています。
不安と期待の眼差し
当時のろうあ者からは、危うくて不安で、そのくせめちゃめちゃ期待されていた様子が、日本聴力障害新聞に載っています。
昭和39年(1964)の日本聴力障害新聞2月号の記事を、参考に紹介します。
『ろうあ者の友となろう』をテーマに企画された“みみずく”創立2周年記念大会は、23名の方々からご寄付をいただき、ろうあ者150名、一般学生や家族など健聴者約60名が集まったことからも分かるように、随分“みみずく”は期待されていたようです。
『京ろう協新聞』1968年10月4日号には、今度、同志社高校、同志社大学の間で、私たちろうあ者のため、友の会を創ろうという動きがでてきました。そして、去る、9月12日の会合で会の名前を『みみずく会』と名付けて正式に発足しました。と紹介されています。
京都市聴覚言語障害センター

昭和53年(1978)7月2日(日)待ちに待った私たちの「聴言センター」の開所式は午前10時30分、式典会場の高野中学校講堂は700人を超える参加者の熱気でムンムンしていました。式典後の祝賀会はセンターの裏手にあたるホリディ・イン・京都で行われました。
厚生省に認可された社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会の、記念すべき第一回理事会は、新しい聴言センターの会議室で6月22日に開かれました。
昭和47年(1972)千本通りを走る市電の廃止。毎年のように値上げされる市電・市バスの運賃。千本北大路のろうあセンターへの交通の便が悪くなってきました。
これがきっかけになってみみずく会の支部作りが始まりました。高野に移ってろうあセンターから京都市聴覚言語障害センターに名称も変わり、規模も少し大きくなりました。
しかし、昭和53年京都の市電は全廃されて、高野の聴言センターへの足がなくなり、支部作りに拍車をかけました。
進々堂
昭和38年(1963)9月12日(木)第二日赤病院の看護学生や京都西陣で働きながら夜間高校や、夜間の大学に通う学生たちが、此処百万遍吉田山のふもと京都大学の近くにある喫茶進々堂に集い、図鑑を見ながら、ああでもない、こうでもないと口角泡を飛ぱし、手話研究会“みゝずく”の名称が決まりました。
この日?最初の名簿に登録された人数は12名。手話学習会“みみずく”に改名したのは昭和42年(1967)12月の臨時総会以降です。
「単に手話を覚えるというような消極的なことではなく、ろうあ協会の行事にも参加してもらって、積極的に私たちの仲間になってもらう」と言うようなことが確認された。と当時の『京ろう協新聞』に紹介されています。京都市からの助成金を受け取るか否かで半年近く議論の末、このお金が自分たちの活動の手かせ、足かせにならないのなら、助成金を快く受けよう。と決定し、今日のみみずく会々則の基礎が出来たのもこの総会でした。
自分たちは昼間働き、夜間に学校へ行き活動しているから、夜行性の動物の名前をと探して見つけた『みみずく』。鳥の『みみずく』の耳は羽毛がはねているだけで本当の耳ではない。ろうあ者の耳も耳の機能が果たせていない。似ているではないか。それに、私たち手話を学び、ろうあ者の耳代わりをやろう。ろうあ者に耳がつく、みみがつく、みみずく、みゝずく と会の名称が決定し、発会の場所として伝説化している喫茶店です。
船岡山公園

昭和40年(1965年)11月18日府立ろう学校高等部生徒によって授業拒否事件が起きました。
この船岡山での写生会に集まったのは先生方だけ。これが後の『3・3声明』引き金になった所。“みみずく”にとってもこの公園は思い出深いところです。
昭和43年(1968)5月5日手話による意見発表会をこの公園の野外ステージで行い、この時のわたし(持田)の意見の不満が、きっかけとなって、以後ろうあ協会の行事は実行委員会形式で、“みみずく”とろうあ協会から役員を出して行事をするようになりました。
船岡山は高さ112メートル、東西200メー卜ル、南北100メートルの丘陵地。
昭和6年(1931)に京都市の都市計画により、船岡山公園が設置されている。
この公園の野外ステージでの手話による意見発表会の様子は、ビデオ『明日を呼ぶ手』にもわずかですが収められています。また、昭和43年(1968)8月25日発行の「ろうあ年鑑」には、参加者全員の意見が収録して載っています。
京都ろうあセンター
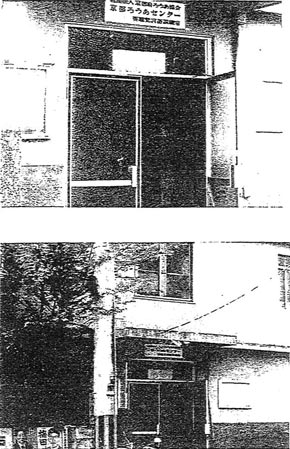
昭和40年(1965)11月18日、府立ろう学校高等部三年生による「授業拒否」と言う、一つの事件がきっかけとなり、翌41年3月3日ろうあ者の人権宣言『三・三声明』が出されました。みみずく会には厚生省社会局更生課から照会があり、それに応えて発足から約3年間の活動のまとめ、『京都における手話奉仕活動の概況とその問題点について』を、京都府と厚生省社会局更生課に提出しました。(昭和41年5月10日)
この年の12月京都府議会で、全国では2例目の手話通訳付きで、ろうあ者が傍聴する中、ろうあ問題が取り上げられました。
当時の知事は、「法律がなければ作ればよい。要求のないところに福祉は育たない。今後はろうあの皆さんの要求にできるだけ応えるようにします。」という回答を得て始まったろうあ会館構想。
ろうあ協会事務所もろう学校から移された。みみずく会例会も勤労会館から千本北大路の旧ライトハウスに移りました。

この旧ライトハウスは、かなり老朽化していて二階の床が抜けるからと言って人数制限があったり、天井や壁がはげ落ちてぶら下がっていました。
昭和35年(1960)10月着工、翌年36年(1961)5月オープン。もっと古いのかと思っていたのに、意外に新しかったので、この歴史散歩で調べみて驚いています。
ニ階の窓の一部は閉まらず、ガラスは割れて雪の降る日は、畳の上に雪が積もって、それでも自分たちの活動の拠点ろうあセンターができたことは何にも増して嬉しかったものです。
ろうあセンターも初めは建物だけから、少しずつ中身も充実するに従い、運動や活動、仕事の幅が出てくると、手狭になって来ました。夢は益々大きくなりついに昭和53年7月、京都ろうあセンターは発展的に解消して、高野に京都市聴覚言語障害センターとしてオープンしました。
現在は視覚障害者協会に返還されて、昭和57年(1982)4月『失明者更生施設鳥居寮』として建物も一新して運営されています。当時の面影といえば施設前の電柱ぐらいです。
セリフの見えるお芝居
昭和40年(1965)みみずく会創立2周年記念を、北区の府立盲学校体育館にて開催しました。
当日の中身はろうあ協会は手話劇『赤ちゃんもってきます』。そして“みみずく会は、手話劇『夕鶴』を上演。そして、ろうあ者の生活実態を来会者に訴えたことが、朝日新聞に取り上げられ『セリフ見えるお芝居』の大きな見出し、笑ったり感動したりの一日でしたと紹介された。
丹後屋旅館
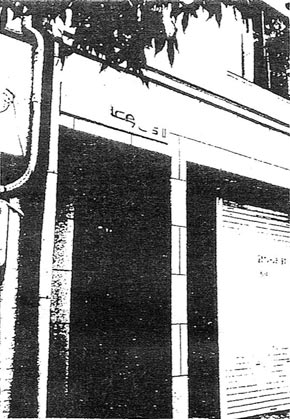
丹後屋旅館は向野先生の自宅で私たち“みみずく”会員にとっては学習の場であり、たまり場でした。ろうあ者に取っては昭和39年(1964)8月の第一・第三金曜日の夜に夜間相談室が開かれ、生活相談の場だったりお茶お花の学習教室の場所でした。他府県から京都に来られた人達には宿泊施設。これが後のろうあセンターのモデルになったようです。みみずくの機関紙や例会ニュースも、向野先生のお宅丹後屋旅館で毎晩のように集まってガリ切りしたり印刷したり。
船岡山の第一回「手話による意見発表会」の原稿も先生の家でガリ切りしました。周りの先輩たちは「こんな原稿は良くない。止めるか書き直せ」。でも、向野先生の奥さんに「うちは、持田君の好きや。おとうちゃん(先生)のや谷さんのは難しいこと言ってはって、よう分からん。かめへん、かめへん、やり、やり」と励まされた原稿が思わぬ波紋を呼んだのも思い出です。ぜひ機会があったら読んでみてください。
中京区の当間さんのお母さんや、上京の吉田さんたちも意見発表しておられます。
最後に、当時のみみずく会長の谷さんが、3年前のろう学校授業拒否問題を取上ながら、『今日のこの意見発表会も、ろうあ者の権利を守る戦いが決して、ろうあ者のためだけのものでなく、我々健聴者の立場をも守るたたかいであることを一層強く確信し、さらには、ろうあ者との連帯を深め、活動したいと思います。ろうあ運動の推進のため、私達通訳の果たす役割は、極めて重要であります。』と、締めくくっています。
当時の“みみずく会”の気概が伺えるかと思い一部を紹介しておきます。
今年は、ろう学校高等部の生徒達が授業拒否をやって42年、昨年はろうあ者の人権宣言である『3・3声明』から40年、この節目の年に、自立支援法案が出されました。介護保険法と支援費制度の統合問題から端を発して、今日の障害者自立支援法、後期高齢者医療制度に私たちや障害者を取り巻く社会保障制度の後退を『3・3声明』を通して学び直してみる絶好の機会かも知れません。
『3・3声明』の中でイソップ童話を引き合いに出して、少年とって楽しい遊び感覚かもしれないが、私たちろうあ者にとっては生死の問題だと訴えている、まさに今の福祉行政の在り方を批判しているとは思いませんか。
第二日赤病院
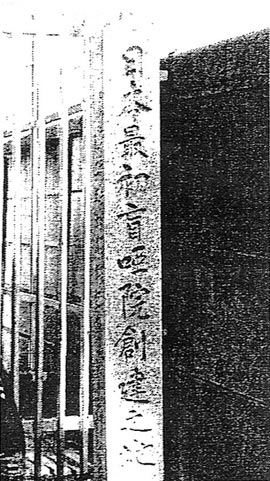
今は第二赤十字病院の脇にひっそり立っている。
昭和38年(1963)1月15日西田一先生が胃潰瘍のため入院されたことがきっかけで、当時の看護学生中島千代美(同志社高校定時制四年生)さんが手まね(手話)を覚えたいと思ったことがきっかけで“みみずく”会が誕生しました。
入院してるんだから文句を言うな!病人だから贅沢言うな!」これって、差別と違うやろか。日頃そんなことを感じていた中島千代美さんは、一人の聾者に出会い「もっとより良い看護がしたい。もっと人間と接したい」と考えました。
明治12年(1879)9月日本初盲唖院がこの地に創建され、その後府立聾学校として、昭和26年(1951)8月5日御室に引っ越すまでの72年間この地で盲・ろう者のための教育がされてきました。
太平洋戦争末期の昭和20年3月14日中等部は勤労動員。予科と初等科の授業も停止。中等部と研究科は鞍馬口の第二教室を改造した学校工場ヘ学徒動員で働くようになりました。24日には、隣接する警察本部長官舎を米軍機の空襲に因る、火災や類焼から守るために、防火帯設置と称して、戦時建物強制疎開が実施され、寄宿舎と食堂の全部と教室の一部、校舎の東北の半分が一挙に引き倒されました。
昭和43年(1968)創立90周年を記念して『日本初盲唖院創建之地』の記念碑が建てられました。